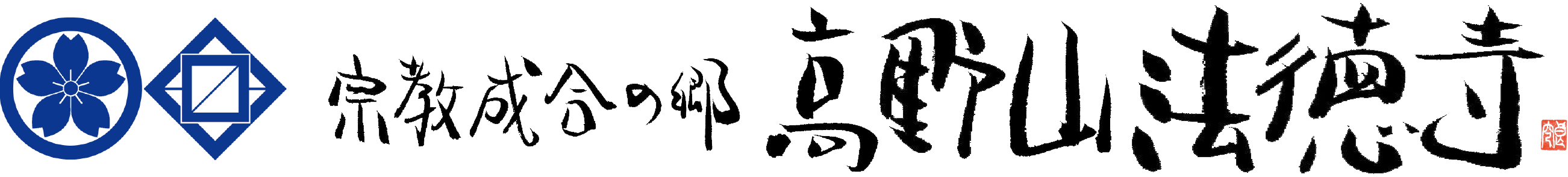幸せさがし─青い鳥の行方(2)

一切衆生悉く皆仏性を有す
幸せになりたいという願いは、生まれた時から具わっている万人共通の願いであると言いましたが、そもそもこの万人共通の願いは、どこから湧いてくるのでしょうか?
その疑問を解く鍵が、『涅槃経』の中にある「一切衆生悉く皆仏性を有す(一切衆生悉有仏性)」という言葉です。
これは、私たち人間だけではなく、動植物や大自然の山々や大地や河川や国土の隅々に至るまで、ことごとく仏となるべき本性(仏性)を有しているという意味ですが、実はこの仏性こそ、「幸せを願う心」が湧いて来る源であると共に、み仏から一人ひとりに授けられた「幸せ」の原石なのです。
「幸せを願う心」を万人が共有しているのは、仏性が万人に分けへだてなく授けられているからですが、実は、願う「幸せ」も、幸せの原石である仏性の中に埋もれているのです。
謂うならば、スタートとゴールが同居しているようなもので、「幸せを願う心」も、求める「幸せ」も、仏性という原石の中で深くつながっているのです。
この事から、私達が願う幸せ(青い鳥)は、自分以外のどこか彼方にあるのではなく、自分の内なる仏性に秘められている事が分かりますが、ただ幸せを願っているだけでは、青い鳥を見つける事は出来ません。
「幸せの青い鳥を探し求めようとする心」を起し、更に一歩前に足を踏み出さなければならないのです。
仏教では、この「幸せ」を「仏」といい、「幸せを求める心」を「菩提心」と言いますが、譬えるなら、「幸せ(仏)」は、「幸せを求める心(菩提心)」の親であり、「幸せを求める心(菩提心)」は、「幸せ(仏)」を親として生まれた子供と言っていいでしょう。
親がいなければ、子供もいないように、「幸せ(仏)」がなければ、「幸せを求める心(菩提心)」もなく、「幸せを求める心(菩提心)」がなければ、「幸せ(仏)」もありません。
「幸せ(仏)」を親として生まれた子供が、もう一人います。それが、「幸せを願う心」です。
「幸せ」と「幸せを願う心」と「幸せを求める心」
この三つは、三位一体の関係にありますが、「幸せを願う心」は、生まれつき具わっている万人共通の心であり、誰もが常に幸せを願っていますから、あえてこの心を意識する必要はありません。
しかし、「幸せを願う心」と言っても、永遠に崩れることのない真実の幸せを願う心もあれば、夢幻のごとき偽りの幸せを願う心もあり、様々な心が、未分化の状態で、渾然一体となっています。
仏性に埋もれている「幸せ(仏)」を掘り起こす為には、渾然一体となっている未分化の心をふるいにかけ、「幸せ(仏)」を掘り起こすのに必要な心を取り出さなければなりません。
こうして取り出された心が、「幸せを求める心(菩提心)」です。
「幸せを願う心」が、私たちに「仏性の中に埋もれている私を早く掘り起こして下さい」といって呼びかける「幸せ(仏)」からのコールサインとすれば、「幸せを求める心(菩提心)」は、「はい、わかりました。これからあなたを求めて掘り始めます」というコールサインへの応答と言っていいでしょう。
「幸せ(仏)」を掘り起こす上で、「幸せを求める心(菩提心)」が欠かせないのは、求める幸せの中味が大事だからです。
み仏が、私達にコールサインを送ってくれているのは、お金や健康や地位や名誉や子供や、その他諸々の条件が満たされる事(欲望の充足)によって得られる偽りの幸せを与えたいからではありません。
何度も言うように、お金や健康や地位や名誉や子供や、その他諸々の条件が叶い、一時的に欲望の充足感が得られたとしても、それは、因縁によって崩れ去るまぼろしのごとき幸せ(此岸の幸せ)に過ぎません。
み仏が私達に与えたいのは、永遠に崩れる事のない幸せ(彼岸の幸せ)であり、だからこそ、「幸せ(仏)」からのコールサインに応える為には、「真実の幸せを求める心(菩提心)」を起す必要があるのです。
勿論、菩提心を起したとしても、み仏を掘り起こすまでの苦難な道のりを考えれば、ほんの小さな一歩に過ぎないかも知れませんが、この一歩を踏み出さなければ、仏性に埋もれた「本当の幸せ(仏)」を掘り起こす大事業は始められないのです。
その意味で、菩提心を起す事は、「幸せ(仏)」からのコールサインに応える大きな第一歩と言っていいでしょう。
み仏をお迎えする
仏性という幸せの原石を与えられていない人は一人もいないと言いましたが、それは万人が幸せ(仏)になれる機会を平等に与えられているという意味であって、誰もが平等に幸せ(仏)になれるという意味ではありません。
幸せになれるか否かは、菩提心を起し、仏性の原石の中に埋もれている幸せ(仏)を掘り出せるか否か、磨きだせるか否かにかかっているからです。
夏目漱石の『夢十夜』の中に、こんな話があります。
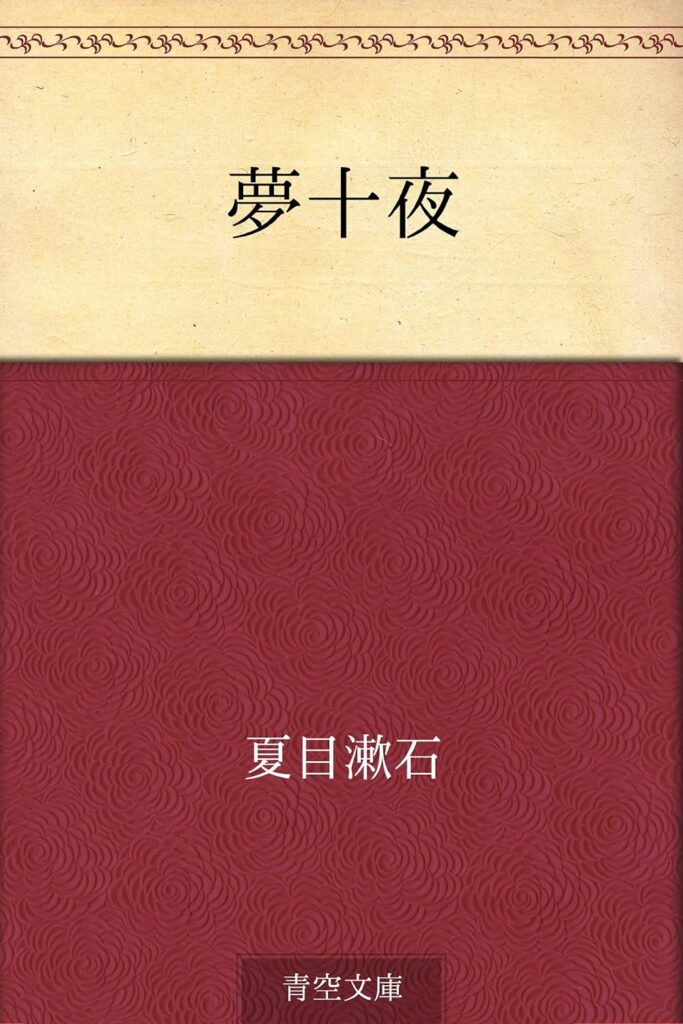
運慶が護国寺の山門で仁王像を刻んでいるというので、見に行った男が、「よくああ無造作に鑿(のみ)を使って、思うような眉や鼻が出来るものだなあ」と、感心しながら独り言を言うと、それを聞いていた別の男が「なに、あれは眉や鼻を鑿で作るんじゃない。あの通りの眉や鼻が木の中に埋まっているのを、鑿と槌の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから決して間違うはずがない」と言ったので、「彫刻とはそういうものか。それなら俺にでもできる筈だ」と思い、すぐ家に帰って、鑿と金槌を持って彫り始めたけれど、いくら木を彫っても、中から仁王は出てこなかったというのです。
運慶が彫れば木の中に埋まっていたみ仏が出てきたのに、何故この男が彫ってもみ仏は出てこなかったのかと言えば、運慶は余分な木屑を彫ると同時に、自己の仏性(菩提心)と向き合っていたのに対し、この男はただ木を彫っていたに過ぎないからです。
つまり、木の中のみ仏を迎えられるか否かは、ひとえに自己の仏性(菩提心)と向き合えるか否かにかかっているのです。
京仏師の松久朋琳師も、『仏の聲を彫る』の中で、同じ事をおっしゃっておられます。

「み仏を彫る場合、木ィを持ってきます。木ィには、仏さんの顔なんてあらしません。ただの四角やら三角やらの木ィで、一定の形はありまへん。人間にたとえたら、これが外見上の人間、何某という姿形をした人間でしょうな。
次に、仏のイメージを持って木ィに向う。そうすると、その木ィには、み仏の他に余分な木屑がついてます。それをはつって取ってしまわななりません。これがある間は、単なる木の塊であって、仏とは言えません。
そこで、その余分な木屑を無にする訳です。木屑をみんな取ってしまう。そうすると、仏像という実体が出てくるということになるのですな。木屑という有を無にしたら、空間をつくったら、その分だけ実有が生まれてくる。
わたしが、木の中のみ仏をお迎えするというのは、つまりこの空間をつくるということなんです。普通、仏を彫るというと実像を生ぜしめることのように考えがちですが、実は、実像を生じせしめる空間をつくっているということにもなるのです。
仏性と出会う、それも又同じことやとおもうのですわ。欲とか煩悩という余分な自我の木屑をはつって取ってしまえば、己れを空しゅうしたら、そこに自然と仏性があらわれてくる」
つまり、木の中のみ仏をお迎えするということは、仏を彫ることではなく、仏を覆っている木屑を彫ることであり、木屑を取ってしまえば、中の仏は自ら出てこられると、言うのです。
仏師はみ仏を彫るのが仕事だと考えている世間の常識からすれば、み仏は「彫るもの」ではなく「お迎えするもの」であるという松久師の言葉は意外に聞こえるかも知れませんが、ここには、「仏師の本分は、み仏を彫る事にではなく、み仏を覆い隠している余分な木屑を取り除く事にある」という、松久師の悟りがあります。
まさに逆転の発想と言ってもいいでしょうが、余分な木屑を取ってしまえば、こちらから出向かなくても、み仏の方から姿を現されるから、仏師はただ、出てこられるみ仏をお迎えするだけでいいのです。
菩薩様が作られた『頼め彼岸へ法のふね』の中に、
自己の仏に あいたくば
人に尽して 業垢(あか)除け
仏像(ほとけ)つくるも 木垢(きあか)とる
と詠われているように、求める仏、探し求める青い鳥に会いたければ、迷いや煩悩という余分なものを取り除かなければならないのです。
必要なみ仏との対話
「原木の中のみ仏をお迎えするには、覆っている木屑を取り除きさえすればいいのだ」と聞けば、夢十夜の男のように、誰でも簡単に彫れるように思いますが、そう簡単にはいきません。
木の中のみ仏をお迎えするという事は、木屑を削っている自分と、木屑の中に埋もれているみ仏が一体となって初めて出来るわざだからです。
つまり、もうこれ以上削れば、み仏を傷付けるというくらいまで木屑を取り除く為には、削る自分と、埋もれているみ仏との対話が欠かせません。
木屑を削るとは、同時に、み仏と対話する事であり、仏師は、み仏と対話をしながら、どこまで削ればいいかを片時も離れずに問いかけているのです。
松久師が、「無心に一発、鑿をガァンと入れますと、み仏は必ずお迎えにこられます。わたしは、そのお迎えに従って、ただ、み仏のまわりの余分な木屑を取りのぞいていけば良いのです。そんな時、もう、わたしがみ仏を彫り参らせているのか、彫られているみ仏がわたしなのか、わからんようになってしまうのです」とおっしゃっておられるように、み仏との対話は、彫っている自分と、彫られているみ仏とを隔てている自我の境界がなくなり、自分がみ仏を彫っているのか、彫られているみ仏が自分なのか、分らなくなる無我の境地へ到達して、ようやく完結します。
ですから、運慶と同じように仏性が具わっている筈の夢十夜の男に、仁王が彫れなかったのは、当然なのです。
彼は、み仏との対話が出来ていなかったのですから。
先ほども言ったように、人間を含め、すべての生きとし生けるものには、山川草木のかけらに至るまで、仏性が具わっています。
しかし、この仏性は、謂わば、まだ削られていない原木と同じなのです。
中に埋もれているみ仏をお迎えする為には、もうこれ以上削れば、み仏の体に傷を付けるというところまで削って、削って、削り尽くさなければなりません。
それは、技術でも理屈でも知識でもなく、人生の様々な辛酸をなめ、苦難を乗り越えてきた人だけが為しうる仏との対話であり、試練の中ではぐくまれた悟りの智慧によってのみ開かれる奇蹟の扉なのです。
苦難を鑿として
原木の中の仏を掘り起こすには鑿が、原石の中の仏を取り出すには研磨剤が必要ですが、この鑿や研磨剤に当るのが、人生の中で誰もが遭遇する様々な試練や苦難なのです。
幸せを妨げる厄介者として、みんなから嫌われている苦難や試練ですが、厄介者の烙印を押された苦難や試練こそ、実は、木の中のみ仏をお迎えする上で欠かせない鑿であり、仏性という原石を磨く上で無くてはならない研磨剤なのです。
菩薩様の『道歌集』の中に、
苦しみを 悲しむことより喜べよ
深き悩みが 菩提となるなり
人になれ 人になれよとみ仏は
心苦しめ 人とならしむ
という道歌があるように、人生に悩み苦しみは絶えませんが、み仏は、何の意味もなく苦しみを与えているのではありません。
苦しみを乗り越える事によって仏性の原石を磨き、中から、幸せ(仏)を掘り出してほしいからこそ、泣くに泣けぬ涙で、慈悲(試練)の鑿を打っておられるのです。
ですから、苦しみをいただいたときには、苦しみを悟りに変え、原石を磨くまたとない好機と受け止めなければなりません。
苦しみは、幸せを妨げる邪魔者であるどころか、真の幸せ(仏)をお迎えする上で欠かせない鑿であり、幸せの原石を磨く人生の研磨剤なのです。
苦しみという名の鍵がなければ、幸せの扉は開かないのです。
万劫にも得難き人身なり
先ほども述べたように、『涅槃経』には、私たち人間だけでなく、動植物をはじめ、山々や大地や河川や国土に至るまで、ことごとく仏性が具わっていると説かれていますが、忘れてならないのは、生きとし生けるものの中で、様々な苦難と向き合い、菩提心を起し、み仏と出会えるのは、私たち人間しかいないという事です。
夢十夜の男のように、たとえ人間に生まれたとしても、必ず木の中のみ仏をお迎えできるとは限りませんが、少なくともみ仏と向き合う為には、人間に生まれてくる事が最低条件であり、人間に生まれてこれなければ、その機会さえ与えられないのです。
その意味で、人間に生まれてこれた事は、とても幸せな事なのですが、果たしてその事に気づいている人が何人いるでしょうか。
人間に生まれた私たちにとって、人間に生まれてくる事は、当たり前の既成事実ですが、人間以外の生き物たちにとって、それは至難のわざなのです。
私たち人間は、他の生き物たちから見れば、羨望の的と言ってもいいでしょう。
道元禅師は、『正法眼蔵』の中で、「生死の中の善生、最勝の生なるべし」、つまり、六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)の中で人間界が最も幸せな世界であると説いていますが、何故人間界に生まれる事がそれほど幸せなのでしょうか?
人間に生まれれば、立派な家屋敷に住めたり、美味しいものが食べられたり、好きな所へ旅行ができたり、お金儲けができたり、素敵な洋服が着られたり、文明生活が謳歌できるからでしょうか。
いいえ、それらはみな、はかない朝露のごとき此岸の幸せに過ぎず、道元禅師が言う「最勝の生」である理由ではありません。
人間に生まれて最も幸せな事は、人間に生まれた者だけが、永遠の幸せが約束される仏性と向き合い、六道輪廻の人生に終止符を打てる事です。
つまり、せっかく、仏性という幸せの原木が与えられていても、その原木から幸せ(仏)を掘り出せるのは、人間だけなのです。
六道の中の地獄、餓鬼、畜生、修羅の世界は、苦しみや争いや憎しみだけの世界であるため、仏性と向き合いたいという心(菩提心)を起すゆとりがなく、また天上界は、楽ばかりの世界で、向上心がないため、仏性と向き合いたいという心を起すことが難しいのです。
それに対し、人間界は、苦もあれば楽もあり、心のゆとりもあり、苦しみから救われたいという向上心もあるため、仏性と向き合いたいという心を起こすには、最も適しているのです。
まさに、人間に生まれた私たちは、生まれた瞬間、すでに幸せの半分を叶えられていると言っても過言ではないでしょう。
「万劫(まんごう)にも得難きは人身なり」と説かれているのは、その為ですが、ここにいう「万劫」とは、時間の長さを現す単位で、「劫(こう)」とは、梵語のカルパ(kalpa)を音写した「劫波」を略したものです。
『大智度論』という大乗仏教の書物によれば、1劫は、百年に一度、天女がこの世へ舞い降り、40里四方の大きな岩を薄い羽衣で一度拭い、その岩が擦り切れて無くなるのに要する期間(磐石劫)を現すとも、芥子粒を40里四方の大きな城の中に満たし、百年に一粒ずつ取り出して、その芥子粒が無くなるのに要する期間(芥子劫)を現すとも言われていますが、要するに、それほどの時間を費やしても、人間に生まれてくるのは難しいという事です。