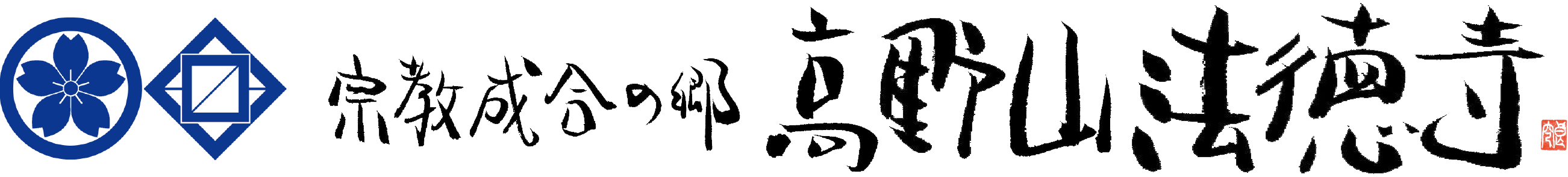幸せさがし─青い鳥の行方(3)

大石順教尼の苦難の生涯
たとえ六道の中で人間界がすぐれた世界であったとしても、仏性を磨き、み仏をお迎えするのは、口で言うほど容易ではありません。
しかし、その道がいかに険しくても、私達は、立ちはだかる試練の荒波を乗り越えていかなければならないのです。
み仏が私達に試練を与えられるのは、苦しめたり挫折させる為ではなく、試練の荒波を乗り越えて、悟りの岸(彼岸)に到達し、永遠に崩れる事のない真実の幸せ(彼岸の幸せ)を手に入れて欲しいからです。
だからこそ、私達が乗り越えられないような試練は、決してお与えになりません。
世の中には、その事を身をもって体現されたお方が何人もおられますが、その内のお一人が、両腕のない尼僧として有名な大石順教尼です。

明治38年(1905)6月21日、大阪堀江の遊郭「山海楼」の主人、中川万次郎が、後妻のお愛と万次郎の甥が駆け落ちした事に腹を立てて逆上し、逃げたお愛の母親のお駒、20歳になるお愛の弟の安次郎、14歳になる妹のおすみ、そして養女にしていた芸妓の梅吉、おきぬ、妻吉の6人に次々と斬りかかり、5人を惨殺するという痛ましい事件が起こりました。
「大阪堀江の六人斬り事件」と言われる事件ですが、この時、両腕を斬りおとされながらも、一命を取り留めた芸妓が、当時17歳の妻吉でした。
妻吉こと大石よねは、明治21年(1888)3月4日、大阪の道頓堀に生まれ、12歳で京舞の名取となり、その才能を見込まれて、15歳の時、中川万次郎の養女となりました。
「妻吉」と名を改めて芸妓の道に精進していましたが、この事件に巻き込まれて両腕を失い、17歳の若さで、この世の生き地獄に突き落とされたのです。
事件を起した中川万次郎は、元は犬養欣也という、尾張徳川家のお殿様お気に入りの小姓でしたが、浮橋という10歳年上の奥女中と深い仲になり、その事がお殿様に発覚してお手打ちになるところを、お殿様の計らいで許され、おひまを出されます。
放浪の旅に出た二人は、やがて別れ、一人で大阪に出てきた欣也が堀江の山海楼で遊んでいるところを、山海楼の一人娘、お八重の眼にとまり、欣也にほれ込んだお八重のたっての願いで、二人は夫婦になります。
欣也は中川家の養子となり、この時から中川万次郎と名乗るのですが、浮橋の亡霊にでも取り付かれたかのように、八重がおかしくなってゆき、やがて万次郎は、おすえという後妻をもらいます。
平凡な夫婦生活が始まりますが、恋多き万次郎は、第三の妻となるお愛と恋愛関係になり、二人の間に女の子が生まれます。
これを好機とばかり、お愛は自分を本妻にするよう万次郎に迫り、万次郎はやむなくおすえと別れ、お愛を本妻にするのですが、お愛は多情な女で、店に来る若い男と仲良くなり、武士上がりの万次郎は、嫉妬心に燃えるようになります。
やがてお愛は、万次郎の甥をそそのかし、二人で駆け落ちをしてしまいますが、武士上がりの万次郎は、自尊心を傷つけられた事がどうしても許せず、ついに6月21日未明、山海楼にいた6人に斬りかかり、5人を惨殺するという大事件を引き起こすのです。
こうして、突然の悲劇に見舞われながら、ただ一人生き残った妻吉の苦難の人生が始まったのですが、両腕を失った妻吉には、舞を踊る両手がありません。
国による生活保障もない時代に、両手を失った17歳の少女が生きる道といえば、見世物芸人くらいしかありませんでした。
そこで妻吉は、三遊亭金馬の一座に入り、「松川屋妻吉」と名乗って、不具の身である自分の姿を見世物にしながら、寄席や地方巡業で生計を立てていたのです。
ところが、ある日、巡業先の仙台で、鳥篭の中のカナリヤが、口で雛に餌を運んでいる姿を見て心を打たれ、自らも筆を口にくわえて書画を書くようになります。
(大石順教尼)
くちに筆 とりて書けよと教えたる
鳥こそわれの 師にてありけれ
学ばざる 身なれど文字を書くという
そのよろこびを くちに筆かむ

明治45年(1912)、日本画家、山口草平と結婚して一男一女の母となりますが、その後、協議離婚し、「堀江六人斬り事件」の犠牲者の冥福を祈るため仏道生活に入り、昭和8年、紀州高野山で出家得度して、名を「順教」と改め、自分と同じように身体に障害を持つ人々の救済に、その生涯を捧げました。
(大石順教尼)
つみふかく あわす手もなき身をもちて
大師のみ子と なるぞ嬉しき
身体障害者の心の母となり、慈母観音と慕われた大石順教尼ですが、書画の道でも日展に入選するなど、その才能を発揮し、昭和37年(1962)には、日本人として初めて世界身体障害者芸術協会の会員に選ばれました。
そして、昭和43年(1968)4月21日、障害者の救済道場として自らが開創した京都市山科の仏光院において、波乱に満ちた81年の生涯を閉じたのであります。
(大石順教尼)
何事も なせばなるちょう言の葉を
胸にきざみて 生きて来し我れ
中村久子さんの無手無足の人生

二人目は、中村久子さんです。
中村久子さんは明治30(1897)年11月25日、畳職人の釜鳴栄太郎、あや夫妻の長女として飛騨の高山に生まれました。
大石順教尼は、両手を斬りおとされましたが、中村久子さんは、2歳の時に、足のしもやけがもとで突発性脱疽(とっぱつせいだっそ)という病気に侵され、両手両足を失くします。
突発性脱疽は、凍傷がもとで両手両足が壊死して腐っていく病気で、放置しておくと、どんどん広がってゆき、命を救うためには、切り落とすしか方法がありません。
お医者さんから「両足とも切断手術をしなければなりません。しかし、幼い子供のことだから、生命の点は保証できません」と宣告されたご両親の悲嘆は、想像に余りあります。
何度も親族会議を開いて相談はするものの、結婚して11年目に授かった可愛い娘の両手両足を切り落とす決断など出来る筈がありません。
しかし、そうこうする内にも病状は悪化の一途をたどり、足から手、手からまた足へと感染していく余りの速さに、お医者さんも手の施しようがありませんでした。
ある日、けたたましく泣き叫ぶ久子さんの声に驚いた母が台所から駆けつけると、左手首が包帯ごと、もげ落ちていました。
そして、その月のうちに、右手は手首から、左足は膝とかかとの中間から、右足はかかとから、切断されてしまったのです。
こうして、久子さんは、命こそ助かったものの、3歳にして、両手両足を失うという、絶句するようなこの世の生き地獄に突き落とされたのです。
しかし、久子さんの本当の試練は、ここから始まったと言ってもいいでしょう。
7歳の夏には、それまで人一倍可愛がってくれていた父が39歳の若さで急死した為、8歳の秋、母あやは再婚を決意します。
病気治療の為に出来た多くの借金と、手足の無い久子さん、そしてまだ幼い弟の栄三を抱えての生活は、女手ひとつでは不可能だったのです。
相手は、亡き夫と同じ畳職人の藤田という人でしたが、藤田家にも、先妻の残した二人の子供がいたため、5歳下の弟は、亡き夫の生家(畦畑家)に預けられ、母は久子さんだけを連れて嫁がざるを得ませんでした。
しかし、障害者に対する偏見の強い時代ですから、再婚先からは温かく迎えてもらえず、久子さんは、肩身の狭い思いをして暮らさなければなりませんでした。
久子さんが一番辛かったのは、一人でお便所に行けない事で、母が来るまで3時間でも5時間でも辛抱して待っていなければなりませんでした。
晩年、久子さんは、「あの時のおかげで、今日旅先で、何時間でもトイレを辛抱することができるようになりました」と述懐しておられますが、8歳そこそこの年齢でよく辛抱されたと、頭が下がる思いです。
9歳の時には一時失明し、眼の見えない久子さんをかかえて困窮した上に、弟の世話をしてくれていた亡き夫の生家(畦畑家)の叔母が3人の子を残して亡くなったため、弟の栄三はやむなく岐阜加納育児院へ引き取られる事になり、ただ一人の弟とも生き別れしなければなりませんでした。
そんな中、祖父母ゆきと母あやは、手足のない久子さんを、何としても一人で生きていける子に育てなければいけないと、心を鬼にして、厳しい躾をするようになります。
その厳しい躾のお陰で、久子さんは食事、トイレ、風呂といった身の回りの事は勿論、裁縫や編み物、炊事、洗濯といった事まで自分で出来るようになりました。
その当時(大正初期)でも、生活困窮者や肢体不自由者には国から最低生活が保障されていましたが、久子さんは、何年このような支給を受ければ自活できるかの目途もたたない上に、世の中のために何一つ役に立っていない自分が、お国のお金を頂くのは申し訳ない、手足がなくても生きている以上は、自分で働いて生き抜こうと決心され、保障を受けませんでした。
久子さんは「運命はみずから開拓す」という言葉を心に刻み、たとえ手足がなくても、人間としてのいのちを頂いたからには、どんなに世間が冷たくても、頂いたいのちを生き抜く事を、自らに誓っていたのです。
その後、見世物小屋で働き始めた時も、「恩恵にすがって生きれば甘えから抜け出せない。一人で生きてゆこう」と、国の障害者制度による保障を受けようとはせず、自分で出来る事は自分でしなければいけないという自立精神は、生涯を貫いて変わることはありませんでした。
しかし、そうは言っても、無手無足の久子さんが、誰にも頼らずに一人で生きていけるほど、世間は甘くありません。
亡き父の友人の助言もあり、久子さんは悩みぬいた末に、見世物芸人として生きる決心をします。
当時、見世物芸人の世界は、生まれつき体に障害を持った人や、社会から受け入れられなかった人の集まりで、白い眼で見られていた時代ですから、相当な覚悟がいったでしょうが、久子さんには、この道しか生きる道がなかったのです。
大正5年11月16日、久子さんは、見世物芸人になるため、高山をあとにし、大正5年12月1日、「だるま娘」の看板で、名古屋大須の見せ物小屋で働くようになります。
両手のない体で、口に針をくわえて裁縫や編み物をしたり、筆をくわえて字を書いたりする芸を披露して、忽ち人気者になっていきました。
ある日のこと、久子さんが舞台に上がっていると、客席から、「これを書いて下さい」という声がかかり、見ると、二十歳前後の青年が「精神一到何事不成」と書いた紙を持っていました。
その青年こそ、後に書道の大家といわれる沖六鳳(おきろっぽう)の若き日の姿で、翌日から、この青年が久子さんに書の手ほどきをしてくれる事になりました。
この時、若き日の沖六鳳がいった「見世物小屋の芸人であっても、人生の泥沼に染まってはいけません。人間としての自分を磨き、”泥中の蓮”にならなければいけません」という言葉は、のちの久子さんに大きな影響を与え、苦難にあうたびに、心を慰められ、励まされたそうです。
沖六鳳との交流は、その後も途絶えることなく、久子さんが亡くなるまで続けられました。
こうして、人気者となった久子さんは、全国各地を巡業して歩くくようになりましたが、巡業先は、日本国内にとどまらず、遠く朝鮮、台湾、満州にまでも及びました。
しかし、いくら人気を博しても、不具の体を人前に晒して糧を得る生き方に変わりはなく、自立する事は出来ても、久子さんにとって、決して生きがいのある人生ではありませんでした。
そんな久子さんに追い討ちをかけるかのように、過酷な試練は容赦なく襲いかかり、大正9年5月には弟の栄三(19歳)を、8月には母あやを相次いで亡くしました。
大正10年、中谷雄三(なかたにゆうぞう)氏と結婚し、翌年長女・美智子さんが産まれますが、大正12年9月には祖母ゆきが、そして9月25日には夫の雄三が30歳の若さで相次いで亡くなります。
しかし、残された娘を育てていかねばならない無手無足の久子さんには、悲しんでいる暇などありません。障害を持った女性が生きる道は、見世物芸人しかなく、興行先との掛け合いから小屋掛けに至るまで、男手がなければ何も出来ない久子さんは、大正12年11月、周囲の勧めもあり二人目の夫となる進士由太(しんしよした)氏との再婚を決意します。
翌年8月、次女富子さんが生まれますが、ようやく軌道に乗りかけたと思ったのも束の間、2年後の大正14年10月24日、再婚した夫が急性脳膜炎で35歳の若さで急死するのです。
五体満足の人でも、二人の幼児を抱えた女性が生きていくのは大変な時代に、無手無足の久子さんは、頼りとしていた夫の突然の死という試練に再び直面したのです。
いつまでも浮き草のような芸人生活をしていては子供達の将来によくないと考えた久子さんは、定住するために職を求めて歩き回りましたが、手足の無い、子供をかかえた女性が働くところなどあろう筈がありません。
重い障害を持った者には、働く場所を確保することさえ難しい時代だったのです。
やはり、久子さんが生きる道は、見世物芸人しかなく、再び巡業の旅に出ますが、久子さんに同行してくれたのは、定兼俊夫(さだかねとしお)という人でした。
ところが、定兼の妻が、巡業中に二人の子を残して急死したため、妻を亡くした男と、夫を亡くした久子さんは、いつしか心を寄せ合うようになります。
二人の夫を見送った久子さんは、再婚をためらいますが、見世物芸人として生きていくためには男手が欠かせす、久子さんは悩んだ末に、大正15年、三人目の夫となる定兼俊夫氏と再婚します。
しかし、定兼は、お酒と勝負事と女遊びが三度の飯より好きな人で、昭和2年4月、興行先の台湾で三女の妙子さんが生まれますが、夫の遊興癖は一向に治まりませんでした。
翌年、まだ1歳にもならない妙子さんが、はしかに罹って急死するという悲しみに遭遇し、二人の夫の死につぐ可愛い娘の死に、久子さんは大きな悲しみとショックを受けます。
昭和4年夏、子供の将来を考えて定住する事を決意し、仕立物をしながら姫路市の借家に住んでいた久子さんは、『キング』という雑誌に載っている記事に釘付けになりました。
そこには、重度の障害で寝たきり状態でありながら、神戸女学院の購買部を立派にきりもりして自立している座古愛子さんの事が紹介されていました。
久子さんは、その時受けた感銘を、『こころの手足』の中で、次のように書いています。

結婚されず、もちろんお子様もない。ほんとうの一人ぼっち。
それなのにあの神々しいまでのお顔は一体どうされたことだろう。
どこから何を得られたのだろう。
お別れする時、私のためにお祈りして下さった、泣きながら真心こめて……。
座古さんと私とどちらが不幸なのだろう?
結婚生活は決して仕合せではなかった。しかし夫が居る。子等も二人ある。不自由な体とはいえ行きたい所へ行くこともできる。
一体自分は何が不足なのか? 手足は無くとも、どうにか一人の女として育てて下さった親があったお陰ではないか。
一寸も自分で動けぬお体であっても、親に一言の御不平もおっしゃらず、他人の幸福を神様に祈って下さるそのことを思ったら、私は何という罰当りではないだろうか?
それまでの久子さんは、無手無足のわが身を見る度に、両親を恨み、わが身を呪い、世を呪って生きていました。
しかし、自分よりも大きなハンディを背負いながら、自分を産み、生かし、育てて下さった両親や、神と周囲の人々への感謝の気持ちをもって生きている座古愛子さんの神々しい姿に触れ、どちらが本当に不幸なのだろうと自問自答され、それまで抱いていた母親への間違った思いを懺悔し、悔い改められたのです。
久子さん、33歳での大きな転機となった出会いでした。
手足のないわたしが、今日まで生きられたのは、母のお陰です。
生きて来たのではない、生かされて来たのだと、ただただ合掌あるのみです。

この言葉は、自分よりも不幸な身にありながら両親への感謝を忘れない座古愛子さんとの出会いによって、心の眼を覚醒させられた久子さんの嘘偽りのない心が、そのまま表現された言葉と言えましょう。
しかし、再婚した夫の不身持ちが一向におさまる気配がないため、久子さんは、昭和8年秋、やむなく7年間暮しを共にした夫との離婚を決意します。
そして、昭和9年、四人目となる9歳年下の中村敏男氏と再婚し、ようやく安住の地を見出したのでした。
二人の子供の行く末を案じた久子さんは、再び見世物芸人の生活に終止符を打とうと決心し、親子四人つつましく暮らしていましたが、そんな時、出会ったのが、無我愛の提唱者、伊藤証信師とあきこ夫人でした。
ご夫妻の尽力で久子さんの後援会が作られ、生活は決して楽ではありませんでしたが、後援会から毎月送られてくる援助金の助けもあって、何とか食いつないでいました。
しかし、それまで自分の力で働き自立して生きてきた久子さんにとって、自分の為に作って頂いた後援会とはいえ、人様の恵みを頂いて生きる事は心苦しいものでした。
久子さんは、悩みぬいた末、「どんなに逃げても、やらなければならないご縁のある内はやめることはできない。やめろと仏様がおっしゃるまでお任せすればよい。もしその日がこなければ、いつまでも芸人をやればよい。すべて仏様にお任せしよう」という心境に到達され、後援会を解散して頂いたあと、再び見世物芸人の道に戻る決心をするのです。
昭和12年の四月、東京日比谷公会堂において、来日したヘレンケラー女史と出会い、自ら口を使って作った日本人形を贈りますが、ヘレンは、久子さんの全身を指先で触れていき、久子さんの足に付けられた冷たい義足に触れた瞬間、久子さんの足元に崩れ落ち、涙を流しながら彼女を抱きしめ、「私を世界の人たちは奇跡の人と言うけれど、あなたこそ、真の奇跡の人です」「私よりも不幸な人。そして私より偉大な人」と言って賞賛しました。
その後、ヘレンケラー女史は二度来日しますが、久子さんはその都度ヘレンケラーと再会され、自ら作った日本人形を贈られました。
昭和17年1月、45歳になった久子さんは、26年間も続いた見せ物芸人の生活に終止符を打たれ、72歳で亡くなる直前まで、夫と次女の富子さんと共に、全国各地で講演活動を続けながら、自らの数奇な人生を語り続け、多くの人々の心に生きる勇気と感動の火を灯し続けました。
講演では、自分の体について恨み言は一言も言わず、「無手無足は、み仏より賜った身体、生かされている喜びと尊さを感じます」と語り、障害のおかげで強く生きられる機会を貰った事への感謝の言葉を連ね、「人間は肉体のみで生きるのではなく、心で生きるのです」と語り、多くの人々に感銘を与えました。
そして、72歳になった1968年(昭和43年)3月19日、脳溢血により高山市の自宅で、波乱に満ちた生涯に幕を閉じられたのであります。
さきの世に いかなる罪を犯せしや
拝む手のなき 我は悲しき
手はなくも 足はなくともみ仏の
慈悲にくるまる 身は安きかな
自分ほど幸せな人間はいない
この他にも、頚椎損傷によって手足の自由を失いながら、口で筆をとって詩を書き、絵を描いて、多くの人々に感動を与えておられる星野富広氏や、交通事故によって頚椎を損傷し半身不随となりながらも自立し、頚椎損傷者や多くの障害者の支援に生涯を捧げられた向坊弘道氏(平成18年5月14日死去)のような方々が大勢おられますが、生き地獄のような逆境に突き落とされたこれらの方々に共通している点が一つあります。
それは、「自分ほど幸せな人間はいない。障害を負ってよかった」と言い切っておられる事です。
五体満足な人間が、「私は幸せです」と言うのであれば分りますが、両手や両足を失い、体の自由を失って、この世の生き地獄に突き落とされた方々の口から、「私は幸せです」という言葉が出てきたのです。
実は、この方々と同じ事を仰ったお方が、もう一人おられます。それは、菩薩様です。
菩薩様も、この世の生き地獄のような代受苦行の真っ只中で、「有り難い」と仰ったのです。
「有り難い」「幸せだ」という言葉は、一般的に考えると、自分の思い通りになっている時に出てくる言葉です。
ところが、菩薩様は、人生で最も苦しい状況に置かれている中で、「有り難い」「幸せだ」と仰ったのです。
菩薩様の言葉や、これらの方々の体験談を聞いていますと、一つの真理が見えてきます。
それは、心(思い方)が変われば、生き地獄が極楽に変わるという事です。
両手両足を失い、寝たきりの状態になりながら、「自分ほど幸せな人間はいない」と言い切れる心は、まさに奇蹟と言っても過言ではないでしょうが、一体どんな心になれば、そんな事が言えるのでしょうか。
大石順教尼も中村久子さんも、星野富弘氏も向坊弘道氏も、そして菩薩様も、生き地獄のような状況に背を向けることなく、在るがままを受け入れ、すべてを拝まれました。
つまり、自分の不幸な境遇や、自分が置かれている苦しい現実から逃避せず、すべてを在るがまま受け入れ、その苦難の現実を拝む心になった時、人生が180度変わり、自分のいる場所がそのまま極楽となり、永遠に滅びない幸せの蕾が花開いたのです。